2025.07.30
書類選考で落ちる人の共通点とは?インターン合格への第一関門突破術
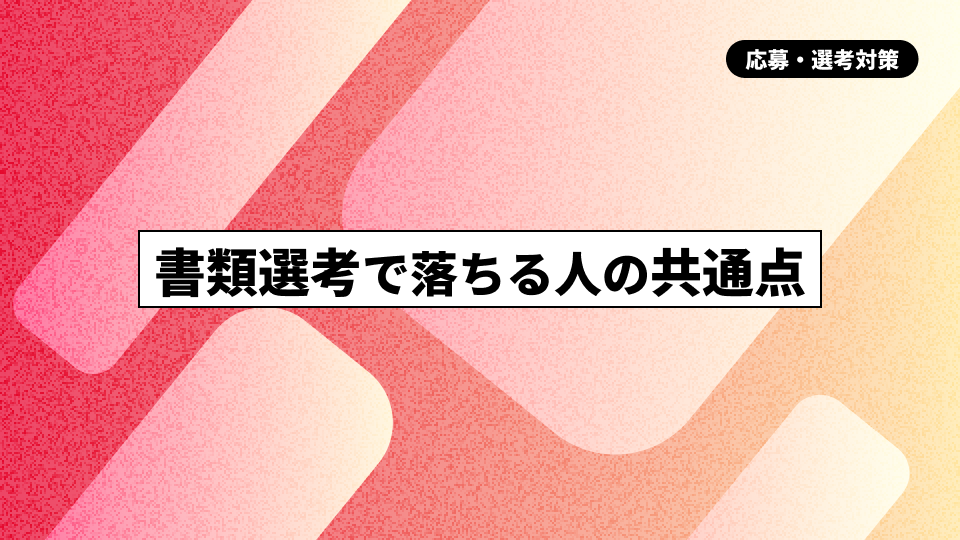
インターンに応募するとき、最初に立ちはだかるのが書類選考。
せっかく時間をかけて履歴書やエントリーシート(ES)を書いても、なぜか通過できない…そんな経験をした方も多いはずです。
実は、書類選考で落ちる人にはいくつかの共通点があります。
今回はその典型パターンと、突破するための対策をお伝えします。
1. 「とりあえず応募」感が透けて見える
採用担当者は、数十〜数百件の応募書類を目にします。
その中で一番目立つのは、**「テンプレ感」や「やっつけ感」が漂う書類」**です。
- 志望動機が「成長したい」「勉強したい」だけ
- 企業名や業界の特徴に一切触れていない
- 他社にも使い回しできそうな文章
これでは、「うちじゃなくてもいいんだな」と判断されてしまいます。
対策:
- 応募先企業の事業内容や理念を調べ、自分の経験や興味と結びつける
- 志望動機は**「あなたの会社だからこそ」**という理由を入れる
2. 書類の基本ルールを守れていない
意外と多いのが、「書類の書き方」そのものが原因で落ちるパターンです。
- 誤字脱字
- 写真が暗い・スナップ写真を流用
- 日付や署名が抜けている
- フォントや形式がバラバラ
採用担当者にとって、こうしたミスは**「社会人としての基礎力不足」**のサイン。
どんなに中身が良くても、第一印象で損をします。
対策:
- 書類は提出前に必ず第三者にチェックしてもらう
- 写真は証明写真スタジオで撮影
- フォーマットや指示は100%守る
3. 自己PRが「自分語り」になっている
自己PR欄でやってしまいがちなのが、「事実の羅列」や「武勇伝」になってしまうこと」。
例:
サークルで100人をまとめる代表を務めました。大変でしたが、やりきりました。
これでは「で、何を学んだの?」という疑問が残ります。
企業が知りたいのは**「その経験から得た力を、仕事でどう活かすのか」**です。
対策:
- 経験 → 工夫や行動 → 成果 → 応募先での活かし方 の順で書く
- 数字や具体例を使って説得力を出す
4. 経験が学業だけに偏っている
大学生の多くは、学業やサークル活動の話が中心になりがちですが、企業は**「実践的な行動経験」**にも注目します。
- アルバイトでの顧客対応
- 学外イベントやボランティア活動
- 個人でのプロジェクトや挑戦
こうした学外経験は、社会での適応力や主体性を示す材料になります。
対策:
- アルバイトや課外活動も自己PRに活用
- 小さな経験でも、学びや改善点を具体化する
5. 「やりたいこと」が曖昧
書類で「とりあえずやってみたい」「何でも挑戦したい」と書くと、一見ポジティブに思えますが、選考では弱い印象になります。
企業は、「目的意識を持って参加する人」を求めます。
やりたいことが曖昧だと、早期離脱やミスマッチのリスクがあると判断されるからです。
対策:
- 「何を学びたいか」を明確にし、それが応募先の環境でどう叶えられるかを書く
- 将来像やキャリアイメージと絡める
書類選考を突破する3つの鉄則
- 企業研究をして“志望理由”を具体化する
- 書類の形式・ルールは完璧に守る
- 経験は成果と学びまで言語化する
ZEROWORKSなら、書類通過後の力も磨ける
ZEROWORKSの長期インターンは、単なる「お試し職場体験」ではありません。
実際の営業実務を通して、自分の強みを明確にし、成果を数字で語れる力を身につけられます。
- 学業以外の経験が増える
- 成果を履歴書で具体的にアピールできる
- 社会人としての基礎スキルが磨かれる
結果として、次のインターンや就活でも書類選考突破率が飛躍的に上がるはずです。
まとめ
書類選考で落ちる人の多くは、「内容以前の基本的なミス」や「説得力不足」が原因です。
これは、ちょっとした意識と準備で改善できます。
今からできることは、
- 応募先の研究
- 自己PRの言語化
- 第三者チェック
そして、実践経験を積むこと。
もしまだ学業以外の経験が不足していると感じるなら、ZEROWORKSのような実践型インターンに挑戦するのが最短ルートです。
あなたの書類が、採用担当者の目に「ぜひ会ってみたい」と映る一枚になるよう、今から準備を始めましょう。