2025.06.01
大学の授業とインターン、どっちを優先すべき?後悔しない選択とは
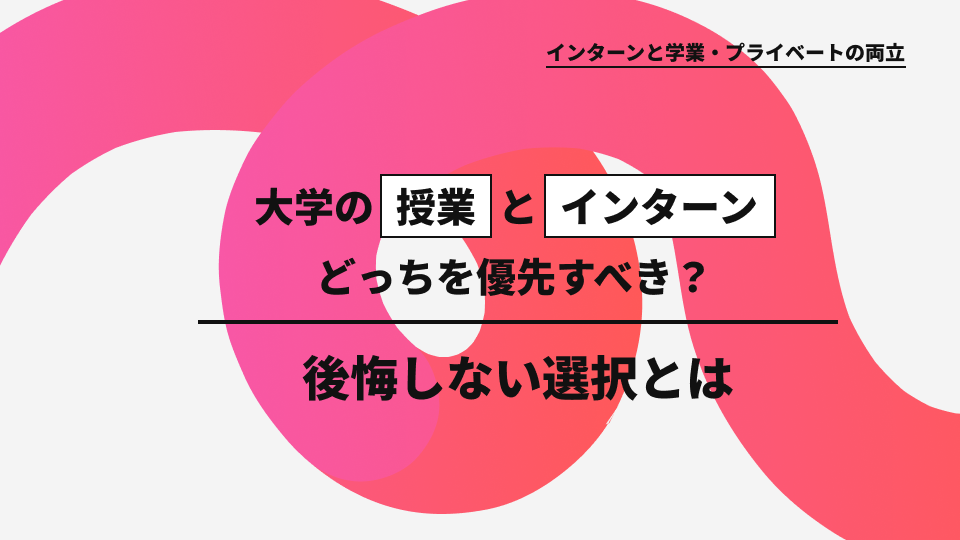
はじめに
長期インターンを検討している大学生の中で、「授業を減らしてインターンに集中するべきか」「学業を優先してインターンは控えめにするべきか」と悩むケースは少なくありません。特に、都内での営業職やオフライン型の有給インターンは拘束時間も長く、両立の難しさに直面しやすいのが現実です。
本記事では、大学の授業とインターンのどちらをどのタイミングで優先すべきかを、目的別・状況別に整理し、後悔のない判断をするための考え方と行動指針を具体的に紹介します。
1. そもそも「どっちを優先すべきか」に正解はない
両立が前提であることを認識する
- 社会に出てからも「複数のことを同時に進める力」が求められる
- 「授業もインターンもやる」選択を前提にした上で、どう配分するかを考えることが大切
学年・目的によって優先順位は変わる
- 1〜2年:基礎的な教養やGPAをしっかり確保する時期
- 3〜4年:就活準備、実務経験の獲得が重要になるタイミング
2. 授業を優先すべきケース
ケース①:単位取得に不安がある場合
- 単位を落とすと卒業に響く → 絶対に避けるべき
- 特に専門科目や必修科目の未履修は後々まで影響
ケース②:志望業界に直結する学びを得られる授業
- 例:マーケティング志望者が市場調査や統計分析の授業を履修している
ケース③:GPAを就活で活用したい場合
- GPAは外資系・大手企業のESで問われることもある
- 一部調査では「GPA3.5以上」でエントリー通過率が約1.3倍というデータも(2022年 就活動向調査)
3. インターンを優先すべきケース
ケース①:実務経験を積んでおきたい職種を志望している
- 営業、マーケ、コンサルなど“実力主義”が強い業界では、経験が重視される
- 例:営業職で3ヶ月以上のインターン経験があると、選考通過率が約1.8倍(2023年 調査)
ケース②:長期インターンの評価制度や裁量が大きい場合
- 成果を出せば「内定直結」「推薦」「リーダー登用」などの機会がある
ケース③:学業の負担が少ない学期(履修コマ数が少ないなど)
- 履修が週2〜3日で済む → 残りの日数を業務にあてられる
4. 判断基準:自分の「目的」と「ゴール」に立ち返る
目的思考で選ぶことが重要
- 「なぜインターンをしたいのか」「なぜこの授業を受けるのか」
- 将来に直結するスキル・実績を得られる方を優先する
キャリア軸で考える
- 就職したい業界や職種に対して、どちらが“説得力ある経験”になるかを基準にする
5. 授業とインターンを両立した学生の実例
ケース①:週3日インターン+GPA3.8を両立(大学3年・営業職)
- 月水金:インターン/火木:授業+課題時間を確保
- 学業ではゼミ論文発表でも評価され、インターンでは商談成約率20%超
ケース②:フル単維持+内定獲得(大学4年・人材系内定)
- 前期に授業を集中 → 後期は週4インターンにシフト
- ESに実務経験とGPAを両方アピールできたことで評価された
ケース③:授業を一時優先 → 後期からインターンで成果(大学2年)
- 春学期:専門授業と資格取得に集中
- 秋学期:履修を減らして週3インターンへ → 営業成績3ヶ月連続チーム1位
6. 両立するための実践Tips
① 時間割作成時点で出勤日を想定する
- 空きコマや移動時間を把握し、勤務可能日を確保したうえで履修登録
② 提出期限・試験時期は早めにリスト化
- GoogleカレンダーやNotionで可視化
- 業務が重なる週は事前に相談・シフト調整を依頼
③ 授業とインターンを結びつけて考える
- 例:授業で学んだ顧客心理を営業トークに応用 → 成約率UP
④ 成果の可視化で“優先の判断軸”を持つ
- GPA、成約率、提案件数などのデータを記録し、成長を実感できるか確認する
まとめ
大学の授業とインターン、どちらか一方だけを選ぶのではなく、**「どちらをどのタイミングで、どのように優先するか」**が重要です。
- 目的とゴールから逆算して選択する
- 授業とインターンの関連性を見つけて相乗効果を狙う
- 両立するための時間管理術を磨く
「どっちか」ではなく「どちらも活かす」視点で選択できれば、後悔のない大学生活とキャリア形成につながります。