2025.05.22
「とりあえずやってみる」は危険?目的意識を持つことの重要性
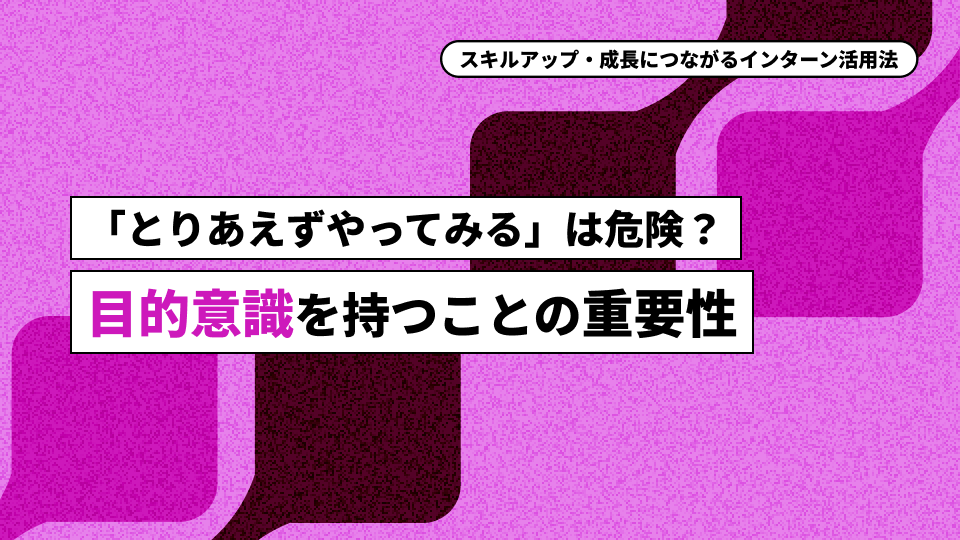
はじめに
「とりあえずインターンに参加してみよう」と考える学生は多くいます。実際に、長期インターンの敷居は年々下がり、都内の営業職やオフラインの有給インターンでも学生を受け入れる企業が増えています。
しかし、明確な目的意識を持たずにインターンに参加すると、「思っていたのと違った」「何も得られなかった」「就活で活かせなかった」と後悔することにもなりかねません。
この記事では、なぜ目的意識が重要なのか、その背景と実際に目的を持って行動した学生の成果例、目的設定の方法などを定量情報を交えながら解説します。
1. なぜ「とりあえず参加」が危険なのか?
① 振り返っても何を学んだか分からない
- 目的なしで動いた結果、学びや成長を実感しにくい
- 面接で「何を得ましたか?」と聞かれて答えに詰まるケースが多い
② 現場でのモチベーションが続かない
- 「とにかく続ける」だけでは、単調な作業に意味を感じられず、早期離脱の原因になる
- 実際、インターン離脱率の理由の第1位は「やりたいことと違った」(マイナビ2023)
③ キャリアに結びつかない
- 目的意識がないと、「将来の志望職種と結びつけられない」
- 例:「営業をやっていたが、結局マーケティング志望で、面接で話が噛み合わなかった」
2. 目的意識がある学生は何が違うのか?
① 成果を出すスピードが速い
- 明確なゴールがあるため、必要な行動が明確になる
- 例:
- 「1ヶ月でアポ数30件を目標」と定めた学生 → 達成のために毎日の行動計画を立て、3週間で目標達成
② 成長を実感しやすい
- 「どんな力を伸ばしたいか」を意識して行動しているため、小さな進歩も評価できる
- 定量的に変化を測定しやすい(例:トーク改善によるアポ通過率の変化)
③ 就活での語り方が具体的
- 「なぜやったか」「何を学んだか」「将来にどう活かすか」が一貫している
- 例:「課題解決力を高めたくて営業インターンに参加→ヒアリング力を磨き、実際に改善提案を行った」
3. 目的設定の方法
ステップ①:なぜインターンをしたいのかを明確にする
- 「何となく不安だから」ではなく、「何を得たいのか」を言語化する
- 例:
- 「営業力を身につけたい」
- 「将来の起業に向けて、顧客理解力を高めたい」
ステップ②:得たい成果を数値で定義する
- 成果目標を具体的な数字に落とし込む
- 例:
- 「3ヶ月でアポ獲得数50件」
- 「提案資料を10本作成する」
ステップ③:そのための行動を週単位で決める
- 数字目標に向けて、週ごとのKPIを設定
- 例:「週15件の架電」「週2回のロープレ参加」など
ステップ④:定期的に振り返りを行う
- NotionやGoogleスプレッドシートで記録を取り、「できたこと」「できなかったこと」「改善点」を明文化
4. 目的意識を持ってインターンに臨んだ学生の成果例
① Aさん(文系・営業インターン)
- 目的:「トーク力と論理的思考力を鍛えたい」
- 行動:トークスクリプトのPDCAを週1回回し、ロープレを継続
- 成果:アポ成功率を8%→22%に向上。就活では「論理的なヒアリング力」として高評価
② Bさん(理系・マーケティング志望)
- 目的:「顧客理解力を身につけ、データ分析と結びつけたい」
- 行動:営業活動を通じて顧客像をメモし、ペルソナ作成→マーケチームに共有
- 成果:提案した施策が実施され、LPのCVRが2.5%→4.1%に改善
5. 目的意識が弱くなったときの対処法
① 初期の目的を再確認する
- 書き出した目的を見返し、「今どこにいるのか?」を整理する
② 上司・メンターに相談する
- 「最近迷っている」「このままで良いか不安」と伝えるだけで、アドバイスが得られる
③ 新たなミッションを自分で設定する
- 現状に飽きてきたら、「後輩育成」「資料改善」など新しい目標を追加する
まとめ
「とりあえずやってみる」という姿勢も悪くはありませんが、それだけではせっかくのインターン経験を最大限活かすことはできません。
- 目的意識があると、成果が出やすく、成長も可視化しやすい
- 目的は数値と行動に落とし込むことで、日々の行動が明確になる
- 目的を持って動いた学生の方が、就活でのアピールが具体的かつ評価されやすい
まずは小さな目的でも良いので、「なぜこのインターンに参加するのか?」を明確にし、そこから逆算して動くことが、後悔のないインターン経験につながります。